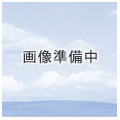- 掲示板
昆虫を食べる事についてどう思われますか?
-
103 匿名さん
皆さん色々と食べてるのね。
感想が聞けて面白いです。
>イナゴの佃煮をもらった。醤油で煮て、一見真っ黒だから小エビの佃煮みたいだった
食べてみたい。
>芋虫は甘エビに似ているらしいよ。
ちょっと食べても良いかもと思った。
>蜂の子はウジそのもの
絶対食べん! -
108 匿名さん
信州、
昔は貧しかったから、蜂の子も大事な蛋白源だった。
その土地の名物と言われる食い物を知ると、その土地の昔のことがわかる。
山形県の名物に大根メシがあるということは、それを年中、食っているほど
あの地の農村が貧しかったということだろう。
京都のお漬物も数々あって、今は、えらい高い土産物になっているが、あんな
ものも庶民の毎日の食事のおかずで、あれでお茶漬けして食ったんだろう。
大してほこれる食い物ではない。 -
109 OLさん
料理は食の貧しい地から生まれた。
何とか加工して食いたい、食わなければ生きることができない、そういう思いで工夫した
結果でしょ?
日本人が”なま”で食べられる魚が沢山あるのは、それだけ日本は食材に恵まれて
いるのよ。 -
110 匿名さん
「昆虫トッピング」のオシャレなチョコレートはいかがですか?http://www.huffingtonpost.jp/2013/10/17/sylvain-musquar_n_4119273.html
フランスのショコラティエが作ったというだけで、オシャレ〜とか言いながらバカ女が食べそう。 -
-
111 匿名さん
昔はそうでも、今は信州でもどこでも、美味しくて栄養のある
食べ物が山ほどある。
不味くて不気味な物を、栄養があるからって無理して食べる必要はない。
それでも残ってるのは、美味しいから、としか理由が思い浮かばない。
それとも飢餓時代を忘れない為、無理して食べてる? -
113 匿名
虫を餌にする川魚、も食べないことにしている。
-
115 匿名さん
虫を食べるのも伝統文化だから。
日本人が、なまの刺身を食べるのも、外国人によっては、非常にテリブル
だと言う人たちもいる。
慣れですよ。
最初にツバメの巣、とか、海鼠なんてよく食ったと思いますね。 -
-
132 匿名さん
昨日(5月26日)NHKのニュースか報道番組で、タイではコオロギなど昆虫を食べる
人が都会地で増えていて、村興しにコオロギを飼って稼ぐ地方の村がある、そうだ。
村人は、『コオロギ』のおかげで、今はクルマが買えたと喜んでいた。
田舎では食べられていた食習慣が、都会地で物珍しさもあって流行りだしたそうだ。 -
133 匿名さん
信州土産のイナゴの佃煮の缶詰を食べたけど、癖があって変な味
遠い昔、信州の母親が作ってくれたイナゴの佃煮は美味しかったのに
母は虫が嫌い、だけど稲刈り後の田んぼでたっぷり捕獲
母はイナゴの佃煮が嫌い、なので砂糖たっぷり甘辛くイナゴの癖を消してしまった
そして、自分は食べなかった
-
-
同じエリアの物件(大規模順)
- THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY (2046戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- シティタワーズ東京ベイ (1539戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- グランドシティタワー月島 (1285戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- グランドシティタワー池袋 (878戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- リビオタワー品川 (815戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ (807戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- パークシティ小岩 ザ タワー (731戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- プラウドタワー池袋 (620戸) | まとめ
- ジオ板橋浮間舟渡 (598戸) | 住民スレ | まとめ
- THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) (578戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- リビオシティ文京小石川 (522戸) | まとめ | スムラボ
- シティタワー武蔵小山 (506戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ
- シティタワー千住大橋 (462戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- シティテラス赤羽 THE EAST/THE WEST (438戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- シティタワー新宿 (428戸) | まとめ | スムラボ
- シティタワー綾瀬 (422戸) | まとめ | スムラボ
- クレストプライムシティ南砂 (396戸) | まとめ
- ブランズタワー大崎 (389戸) | まとめ | スムラボ
- プラウドタワー平井 (374戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- プラウドタワー小岩フロント (367戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ