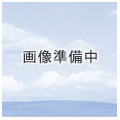- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
やっぱり豊洲が好き 4
-
-
236 匿名さん
プールのある物件は賛否両論ありますよね
利用しなくなったら、管理費がもったいないとか・・・
利用する人のみ管理費を支払うって出来ないのかな。
マンション住民以外も利用できるようにするとか。。。
-
-
241 匿名さん
Doスポーツはすごい人気で時期によってはキャンセル待ちが必要だとか。
プールは25mが8コースもあります。都内ではこんなに大きな室内プールなかなか
ないのではないかな。
エステや整骨院なども入っていてすごく広い施設です。 -
242 匿名さん
Doスポーツってそんなに人気あるんですか!
あらら。
プールだったら有明か月島に行く感じになるんですかね…。
月島は会社帰りに行ったことありますが
そこそこ人はいるけど、でも快適に泳げる範囲でしたよ。 -
245 匿名さん
有明はいいよー。2時間300円で、ちっちゃなスライダーもある。
室内プールだけど、屋根がドーム球場みたいに開閉式になってる。
この時期は、室内プールだと思って日焼け止めしないで行くと、背中ひりひりで
大変なことに。
辰巳も大会とかないときは大丈夫。大会があるときでも、サブプールだけ
解放してたり。
あと夏は、越中島の方のプールも解放してたような。 -
246 匿名さん
結構プール関係は充実しているようですね。
電車やバスでも簡単に移動できるし、自転車でもそもそも行くことができますよね。
有明のプール、室内だと思っていたのですが
屋根あくんですか。
知ってよかったです。 -
-
252 匿名さん
直下型地震が起きた時、東京湾の津波がどうなるか…っていうのが気になる。
それがクリアできれば、通勤的にも周辺施設的にも問題がクリアできるのだけど。
東京湾は構造的には津波が起きにくいとのことだけど
実際起きてみないとわからないからね。。。 -
253 匿名さん
確かに東日本大震災では予想以上の津波に防波堤を突破されてしまいましたが、東京湾の場合は房総半島と三浦半島が防波堤になっているため、半島が沈むくらいの想定外が起こらなければ津波に突破される事は有りませんし、その規模の大震災が起これば関東は壊滅すると思いますよ。
-
-
267 匿名さん
確かに液状化のニュースは印象が強かったし、今後も心配ではあるけど勤務地や学校が近いんだったら今でも十分に検討する価値がある場所だと思います。
個人的にこの辺に住んだときに一番怖いと思うのは帰宅困難時ですね。都心からの帰宅という事を考えると震災時に最悪の場合陸の孤島になりそう。 -
268 匿名さん
これはまずい・・・家の目と鼻の先にこんなのが埋め立てられたなんて・・・
被曝が心配です。豊洲終わったかも・・・
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/20l66101.htm -
276 匿名さん
液状化の報道やネット上の画像を見るとやっぱり自分の住処にするには不安を感じますね。
画像などを見るかぎりだと道路の補修などで移動が不便そう。あとは宅配便が遅れるとかもあったのかな?
生活している方じゃないとわからない不便もあると思いますが実際に液状化した地域に住んでいる方にどんな不便があったかも聞いてみたいです。 -
-
286 匿名さん
あいにく東京都臨海広域防災拠点が有明
東京湾臨海部基幹的広域防災拠点 - 内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/yobishisetu/pdf/rinkai.pdf
を良くごらんよ。
確かに火災地帯に援助救援は難しいかもね。
お気の毒。
-
290 匿名さん
直前に知るのは不可能? 地震予知、なぜ難しいのか
(1/3ページ)2012/11/3付
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO47989540S2A101C1TY1P01/
「予知」の用語、使い方見直し 地震学会「誤解生む」
2012/10/18付
http://www.nikkei.com/article/DGKDASDG1704X_X11C12A0CR8000/
地震「直前予知は困難」 学会シンポ
2012/10/17 1:53
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO47345300X11C12A0CR8000/
日本地震学会の2012年度秋季大会が16日、北海道函館市で始まった。国が地震予知研究を進めるきっかけになった提言書から50年という節目の年でもあり、予知に批判的な専門家も招き、予知の是非を問う特別シンポジウムを開催。大地震がいつどこで起こるかを正確に言い当てる「直前予知」は実現困難との見方でおおむね一致したが、予知研究の防災効果などを評価する意見もあがった。
地震予知の研究を巡っては、専門家の間でも賛否が分かれており、双方が同じ場で議論することは珍しい。地震学会の会長を務める加藤照之・東京大教授はシンポジウムの最後に「今日がキックオフ。今後も地震予知をどうしていくかを議論していきたい」と話した。
昨年の東日本大震災で地震学者らは「想定外」を繰り返し、日本の地震研究への信頼は失墜した。地震学会は今回、問題点を洗い出す狙いでシンポジウムを開いた。
批判の急先鋒(せんぽう)に立ったのは東京大学のロバート・ゲラー教授。「(予知研究に取り組む契機になった)提言書の真の目的は観測網の設置で、予知は予算獲得のスローガンにすぎなかった」と主張し、マグニチュード(M)9.0という巨大地震でも前兆現象がなかった点をあげ、観測網の充実は予知につながらないと指摘した。
カリフォルニア工科大学の金森博雄名誉教授も「地震の発生過程は極めて多様で、予知の実用性は今もって不明」と述べた。
一方、提言書の作成に加わった元気象庁地震火山部長の津村建四朗氏は、津波予報の高度化や地震情報の迅速化などにつながっている点をあげ、「予知計画の予算は予知だけに役立っているわけではない」と反論。東京大の平田直教授も静岡県の伊豆東部の地震はマグマ活動から予測できるようになった点を指摘した。
予知研究で日本は直前予知の実用化を目指し1965年に「地震予知研究計画」を始動、毎年数億円から数十億円の予算をつぎ込み、観測網の整備を進めてきた。
同じエリアの物件(大規模順)
- THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY (2046戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- シティタワーズ東京ベイ (1539戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- グランドシティタワー月島 (1285戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- グランドシティタワー池袋 (878戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- リビオタワー品川 (815戸) | まとめ | スムログ | スムラボ
- パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ (807戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- パークシティ小岩 ザ タワー (731戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- プラウドタワー池袋 (620戸) | まとめ
- ジオ板橋浮間舟渡 (598戸) | 住民スレ | まとめ
- THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) (578戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ
- リビオシティ文京小石川 (522戸) | まとめ | スムラボ
- シティタワー武蔵小山 (506戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ
- シティタワー千住大橋 (462戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- シティテラス赤羽 THE EAST/THE WEST (438戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- シティタワー新宿 (428戸) | まとめ | スムラボ
- シティタワー綾瀬 (422戸) | まとめ | スムラボ
- クレストプライムシティ南砂 (396戸) | まとめ
- ブランズタワー大崎 (389戸) | まとめ | スムラボ
- プラウドタワー平井 (374戸) | 住民スレ | まとめ | スムラボ
- プラウドタワー小岩フロント (367戸) | 住民スレ | まとめ | スムログ | スムラボ